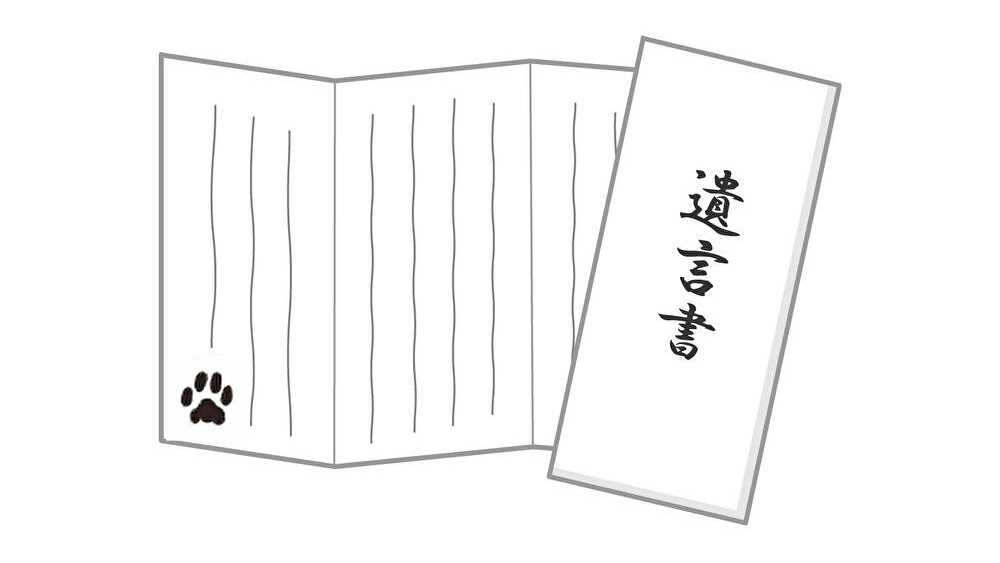こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
「遺言書を作成したい。でも、内容を誰にも知られずに済む方法はないだろうか?」
このご要望にお応えできる遺言方式の一つが、「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」です。民法で定められた3つの普通方式の遺言のうちの一つですが、実は実務上、積極的に利用されるケースは非常に少ないのが現状です。
なぜ利用者が少ないのか?そして、あなたが本当に秘密性を重視したい場合、他にどのような選択肢があるのか?
行政書士として、秘密証書遺言の仕組みから、その利用が推奨されない理由、そして代わりに検討すべき有効な対策まで、詳しく解説していきます。
1. 秘密証書遺言の方式と作成の流れ
秘密証書遺言は、以下の4つの要件を満たすことで法的な効力を持ちます。
- 遺言書の作成と署名押印
遺言者が遺言書を作成し、これに署名・押印します。遺言書の本文は自筆である必要はなく、パソコンや代筆でも可能ですが、署名は必ず遺言者本人が自筆で行う必要があります。 - 封入と封印
- 作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印章で封印します。
- 公証人・証人への提出と申述
遺言者が公証人1名と証人2名以上の前にその封書を提出し、それがご自身の遺言書であることと、氏名・住所を申述します。 - 公証人等による署名押印
公証人が、提出された日付と遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人の全員がその封紙に署名押印します。
手続きが完了すると、封印された遺言書は遺言者が持ち帰り、ご自身で保管することになります。公証役場には、遺言書の封紙の控え(写し)が残るのみです。
2. 秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言は、主に以下の点で他の遺言方式にはない特徴を持ちます。
- 遺言内容を完全に秘密にできる
遺言書は封がされており、公証人や証人はその中身を確認しません。そのため、遺言者が亡くなるまで誰にも内容を知られることなく、遺言の存在だけを知らせることができます。 - 自筆でなくても作成可能
自筆証書遺言と異なり、遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できるため、病気などで自筆が難しい方でも作成が可能です(ただし、署名と押印は必要です)。 - 偽造・変造の防止
公証人や証人の立ち会いのもとで厳格な手続きを経るため、自筆証書遺言と比べて、偽造や改ざんのリスクを低く抑えることができます。
3. 秘密証書遺言のデメリットと注意点
利用件数が少ない秘密証書遺言には、いくつかの大きなデメリットがあります。
- 方式の不備で無効になるリスク
公証人が内容を確認しないため、遺言書の内容自体に法的な不備(例:財産の特定が不明確、遺言能力を欠くなど)があった場合、遺言が無効になる可能性があります。 - 紛失・隠匿・破棄の危険性
遺言書は遺言者自身が保管するため、紛失したり、発見した相続人によって隠匿・破棄されてしまう危険性が残ります。 - 家庭裁判所の「検認」が必要
公正証書遺言と異なり、相続発生後、必ず家庭裁判所で「検認」の手続きを経なければなりません。この手続きには手間と時間がかかり、すぐに相続手続きを開始できないというデメリットがあります(ただし、法務局で保管しない自筆証書遺言も検認が必要です)。 - 証人が必要
公証人以外に2名以上の証人を用意する手間と費用が発生します。
4. 秘密性を確保しつつ確実性を高める代替案
秘密証書遺言のデメリットは、現代の相続対策においてあまりにも大きく、確実性に欠けます。行政書士としては、「秘密証書遺言に固執せず、他の方法で秘密性を確保する」ことを強くお勧めします。
あなたが「内容を秘密にしたい」と考えるなら、以下の2つの代替案をご検討ください。
代替案①:公正証書遺言
- 確実性
公証人が内容をチェックするため、形式不備による無効リスクはほぼゼロです。検認も不要です。 - 秘密性への配慮
遺言内容自体は公証人と証人に知られますが、彼らには守秘義務があります。また、遺言書を誰に渡すか、どう実行してほしいかといった「想い」の部分は、遺言の本文とは別に「付言事項」に記載し、死後に初めて遺族が目にするように工夫できます。
代替案②:自筆証書遺言の「法務局保管制度」
- 秘密性
遺言者が自筆で作成し、法務局に預けるため、内容を誰にも知られることはありません。 - 確実性・検認
法務局で原本が保管され、形式的なチェックも行われるため、紛失・偽造リスクがなく、検認手続きも不要となります。費用も安価で、最もバランスの取れた選択肢と言えます。
5. まとめ
遺言書の真の目的は、「遺言者の想いを確実に実現すること」と「遺された家族が争わないようにすること」です。
秘密証書遺言は、その名の通り「秘密」を守る点では優れていますが、「無効リスクが高い」「検認で手間がかかる」という弱点を抱えています。これでは、遺言者の想いが実現されないばかりか、遺族に争いの火種を残しかねません。
当事務所では、お客様の「秘密にしたい」というご要望と「確実に財産を渡したい」というご要望の両方を叶えるため、公正証書遺言や法務局保管制度の利用を強くお勧めしています。
遺言書は、形式と内容の両面で法的要件を満たし、かつ遺族の気持ちに配慮したものであることが重要です。遺言書の作成を検討される際は、専門知識を持つ行政書士へご相談ください。あなたの希望を伺い、最も安全で確実な方法をご提案いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで