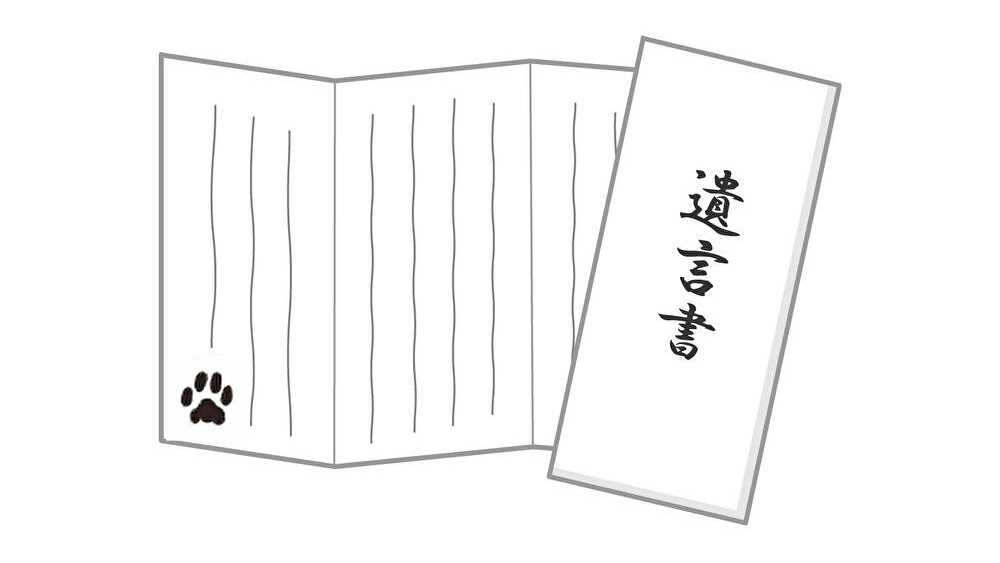こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
相続をスムーズに行うための遺言書には、万が一の事態に備えた「予備的条項」を含めることが非常に重要です。この予備的条項は、指定した相続人が先に亡くなったり、相続を放棄したりした場合に、誰がその相続分を受け継ぐかをあらかじめ定めておくためのものです。
遺言書を作成した後に、上記のような「想定外の事態」が起こった場合に備えるために、遺言書にぜひ盛り込んでおきたい「予備的条項」について、分かりやすく解説していきます。
予備的条項の重要性
遺言書を作成する際、多くの人はまず、誰に何を相続させるかを具体的に定めます。例えば、「長男に自宅不動産を相続させる」といった内容です。しかし、遺言書作成後に長男が亡くなってしまった場合、遺言書に長男の次の受取人が指定されていなければ、その部分の遺産は遺言書が存在しないものとして扱われます。
この場合、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。これは、遺言書を作成した本来の目的である「相続トラブルの防止」や「手続きの簡略化」に反する事態です。予備的条項を設けておけば、このような状況を回避し、故人の意思を確実に実現させることができます。
また、遺言書に「預金1000万円を長男に」と書いていたのに、亡くなった時にその預金がゼロになっていたらどうなるでしょうか?
結論から言うと、その預金に関する遺言は効力を失います。長男は何も受け取れず、遺言者の想いが実現されないことになってしまいます。
予備的条項の種類と例文
予備的条項には、様々なケースに対応するための種類があります。ここでは、代表的なパターンと具体的な例文を紹介します。
指定相続人が先に死亡した場合
最も一般的なケースです。指定した相続人が自分よりも先に亡くなってしまった場合に備えます。
例文:
「遺言者は、その所有する下記不動産を長男に相続させる。ただし、長男が遺言者より先に死亡したときは、長男の子に相続させる。」
この条項があることで、長男が先に亡くなっても、改めて遺産分割協議を行うことなく、長男の子が遺産を受け継ぐことができます。
遺言書に記載した財産内容が変わった場合
遺言書作成後に、記載した不動産を売却したり、預金を使い切ったりと、財産の内容が変わってしまうケースはよくあります。
また、新たに不動産を購入するなど追加される場合もあります。
例文:
「遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を長男に相続させる。 ただし、本不動産が相続開始時に存在しない場合は、売却代金または遺言者の有する現金を、本不動産の価額に相当する限度で長男A相続させる。」
この一文があるだけで、不動産が売却されて現金に変わっていたとしても、長男への相続を実現できます。
包括的な残余財産の指定をする場合
個別に指定しなかった財産(記載漏れや消滅した財産の代わりとなるものを含む)の帰属を、まとめて指定しておく条項です。
例文:
「本遺言書に記載した以外の遺言者の有する一切の財産(または、「残余の財産」)は、長男に相続させる。」
特定の財産がなくなっても、その代わりに手元に残った現金などは「残余財産」として指定された人に渡るため、財産全体をめぐる遺産分割協議の手間を回避できます。
予備的条項を作成する際のポイント
予備的条項を効果的に活用するためには、以下のポイントに注意して作成しましょう。
- 複数の予備的条項を組み合わせる
上記のケースは単独で記載することも可能ですが、「長男が先に死亡、または相続放棄した場合」のように、複数の条件を組み合わせて記載することも可能です。これにより、より多くの状況に対応できます。 - 代襲相続の対象者を明確にする
予備的条項は、代襲相続(被相続人の子が先に亡くなった場合に、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続すること)とは異なる制度です。予備的条項では、遺言者が自由に次の相続人を指定できるため、「孫」だけでなく「配偶者」や「兄弟姉妹」など、誰に相続させるかを明確に記載することが重要です。 - 受遺者(遺贈を受ける人)の場合も考慮する
予備的条項は、相続人に対する相続だけでなく、相続人以外の人(受遺者)への遺贈にも適用できます。例えば、「知人に〇〇を遺贈する。ただし、知人が先に死亡した場合は、知人の子に遺贈する」といった内容です。
まとめ
遺言書は、ただ「誰に何を相続させるか」を記載するだけでは不十分です。未来に起こりうる様々な事態を想定し、予備的条項を適切に盛り込むことで、遺言書が持つ本来の力を最大限に発揮できます。これにより、遺産分割をめぐる家族間のトラブルを未然に防ぎ、故人の意思を確実に次の世代へと引き継ぐことができます。
遺言書の作成を検討されている方は、予備的条項を含めたより詳細な内容について、行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。専門的な知識を持つ第三者が関与することで、法律上の不備がない、より確実な遺言書を作成することができます。
もしもの事態を想定し、予備的条項を含めた間違いのない遺言書を作成したいとお考えでしたら、ぜひ一度、遺言書の作成を専門とする行政書士にご相談ください。
ご家族の状況や将来の可能性を一緒に考え、ご自身の思いを完璧に形にするお手伝いをさせていただきます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで