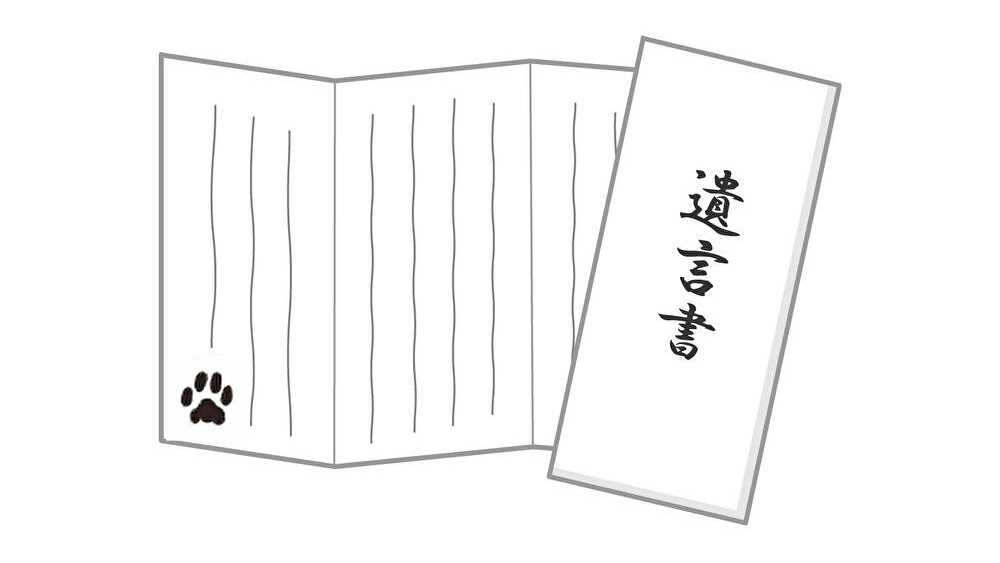こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
以前、掲載した記事の続きです。残りの6つのケースについて見ていきましょう。
⑦相続人に認知症などにより判断能力のない人がいる
遺言書がない場合、こちらも遺産分割協議となりますが、相続人に認知症の人がいる場合、この遺産分割協議が非常に困難になります。
- 遺産分割協議ができない
認知症の症状が進行し、ご自身で判断能力を失っている場合、その方は法的に有効な意思表示をすることができません。そのため、遺産分割協議に参加することができず、その合意も無効となります。 - 「成年後見制度」の利用が必要になる
遺産分割協議を行うためには、認知症の相続人の代わりに、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう必要があります。- 手続きの複雑さと時間:成年後見人の選任には、家庭裁判所への申立て、医師の診断書の提出、面談など、複雑な手続きと数ヶ月の時間がかかります。
- 費用の発生:成年後見人には、専門家が選任されることが多く、その場合、毎月報酬を支払う必要があります。
- 後見人の権限:成年後見人は、認知症の相続人の財産を守るのが仕事です。そのため、本人の利益にならないと判断すれば、他の相続人の希望通りの遺産分割に同意しないこともあります。
- 財産の凍結と手続きの長期化
成年後見人が選任されるまで、遺産分割協議は進められません。その間、預貯金の引き出しや不動産の売却・名義変更などができず、あなたの財産は凍結された状態が続きます。これにより、残されたご家族の生活費や、相続税の納税資金の確保に支障が出る可能性もあります。
⑧法定相続人以外に財産を残したい
お世話になった友人や、可愛がっている孫、あるいは長年尽くしてくれた介護士さんに財産を遺したいんだけど、法律で決まっている相続人以外の人に財産を渡せるのかな…?というご希望もあります。
くどいようですが、上記の方々は法定相続人ではありません。遺言書がなければ、あなたが「この人に財産を遺したい」と強く願っていても、残念ながらあなたの死後、その方に財産が渡ることはありません。
⑨相続人がいない
相続人がおらず、遺言書がない場合に遺産はどうなるでしょうか?
この場合は、最終的には国庫に帰属することになります。しかし、遺言書を作成することで、ご自身の意思に基づき、特定の個人や団体に財産を遺贈することができます。
相続人がいない場合、遺言書で主に以下のようなことを指定できます。
- 特定の方への遺贈
親しい友人、お世話になった方、遠い親戚など、法定相続人ではないけれど財産を渡したい相手を指定できます。 - 団体への寄付
学校、NPO法人、慈善団体など、特定の団体に財産を寄付することができます。社会貢献を考えていらっしゃる方には有効な手段です。 - 特別縁故者への財産分与
もし、生計を共にしていた事実上の配偶者や、献身的に介護をしてくれた親族など、特別縁故者がいる場合、遺言書でその方に財産を遺贈する意思を明確にすることで、将来的な手続きを円滑に進めることができます。
⑩行方不明の相続人がいる
相続人全員の話し合いによって、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める遺産分割協議ですが、相続人の中に行方不明の人がいる場合、どうなるのでしょうか?
全員の合意が必要なため、一人でも欠けるとその協議は無効となります。
まずは行方不明の相続人を探さないといけないのですが、どうしても見つからない場合は、家庭裁判所に申し立てをして、相続手続きを進めることになります。主な手続きは以下の2つです。
- 不在者財産管理人の選任申立て
行方不明の相続人(「不在者」といいます)に代わって、その財産を管理し、遺産分割協議に参加する人(「不在者財産管理人」)を家庭裁判所に選任してもらう制度です。 - 失踪宣告の申立て
行方不明の状態が長期間続いている場合に、その人を法律上死亡したものとみなす制度です。失踪宣告がなされると、その時点から相続が開始されたものとして、他の相続人だけで遺産分割協議を進めることができます。
いずれも場合も手続きに時間がかかり、その手続きが完了するまでは相続手続きを進めることができません。
⑪会社経営者、個人事業主である
会社経営者や個人事業主の方にとって、遺言書は単なる個人の財産分与に留まらず、ご自身の築き上げてきた事業の行く末をも左右する非常に重要な意味を持ちます。適切な遺言書を作成することで、事業承継を円滑に進め、残されたご家族や従業員、取引先への影響を最小限に抑えることができます。
以下の点を遺言書に盛り込むことを検討しましょう。
- 自社株式の承継先
- 後継者の選定と株式の集中: 経営権の安定のため、自社株式は後継者(ご子息、信頼できる役員など)に集中させることを検討します。株式が分散すると、経営方針の決定に支障が出る可能性があります。
- 議決権の行使に関する指示: 誰にどのような議決権を行使してほしいか、具体的な指示を盛り込むことも可能です。
- 少数株主への配慮: 少数株主がいる場合、その権利にも配慮した記述が必要となる場合があります。
- 事業用資産の承継
会社名義の資産だけでなく、個人名義で事業に使用している不動産や設備がある場合、その承継についても明確に定めます。 - 事業資金・債務の処理
- 会社の運転資金: 会社が借り入れている資金や、個人の連帯保証などがある場合、その処理方法について言及することで、後継者の負担を軽減できる可能性があります。
- 個人事業の債務: 個人事業主の場合、事業に関する債務の承継についても明確に定めます。
まとめ
2回にわたって遺言書を書いたほうがいいケースを紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
「あ、あてはまる」という方もいらっしゃったのではないでしょうか。
遺言書は、単に財産をどう分けるかを記すだけのものではありません。それは、残される大切なご家族や関係者への深い思いやりを表すものだと私は考えています。
ご自身の意思が確実に反映されるように、そして何よりも、残される方々が安心して生活できるように、「まだ早い」と思わずに、ご自身の「もしも」に備えましょう。
遺言書についてもっと詳しく知りたい、あるいは実際に遺言書の作成を検討したいという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの想いを丁寧にヒアリングし、最適な遺言書の作成をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで