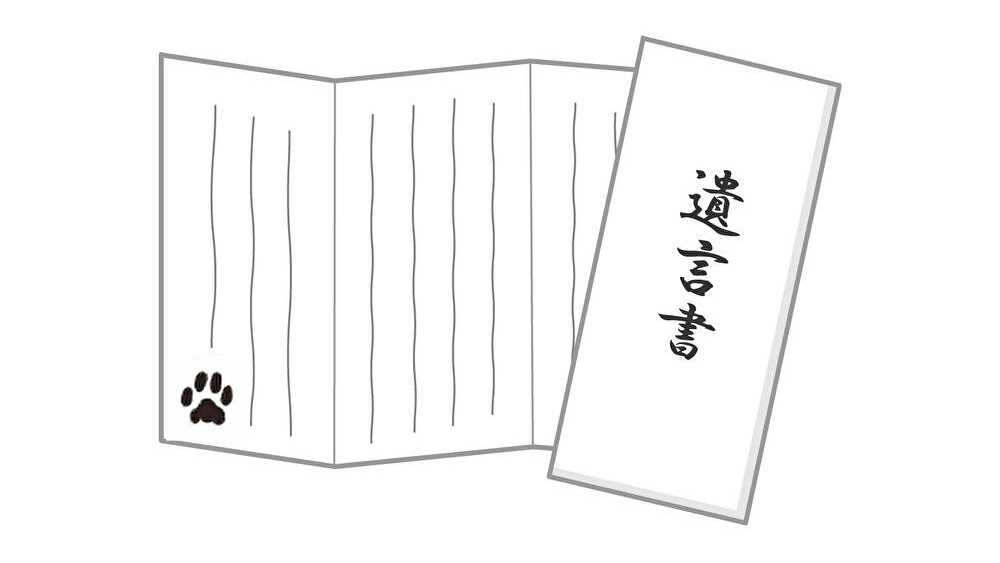こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
行政書士として相続の相談に乗っていると、「もし遺言があれば…」と思うケースにたびたび遭遇します。遺言は、ご自身の死後、財産をどのように分けたいかを明確に示せるだけでなく、残されたご家族がスムーズに手続きを進めるための大切な手段です。
では、どのような人が遺言を書いておくべきなのでしょうか。
具体的なケースを2回に分けてご紹介します。
① 自分で遺産の分配内容を決めたい人
ご自身の中で「こうしたい」という明確な希望があったとしても、遺言書という形で残されていなければ、それは単なる「希望」にとどまり、法的な効力は持ちません。ご自身の財産を誰にどれだけ分けたいかという希望がある場合は、遺言が不可欠です。例えば、
- 特定の相続人に多く財産をあげたい
長男に家業を継がせるため、他の兄弟よりも多くの財産を残したい場合など - 特定の相続人には財産をあげたくない
疎遠になっている相続人がいる場合など
※いずれも、遺留分には配慮が必要です
遺言書がない場合、原則として、残されたご家族(相続人)全員で話し合い、「遺産分割協議」によって遺産の分け方を決めなければなりません。
②相続人同士の仲が悪い
残念ながら、相続は、普段は仲の良い家族であっても争いの火種になりやすいものです。ましてや、元々関係性が良くない相続人同士の場合、遺言書がないと、ほぼ確実に「争族」になってしまう可能性が高いと言えます。もし、あなたが相続人同士の不仲を心配されているのであれば、遺言書は「必須」の対策です。
遺言書がない場合、遺産は原則として「遺産分割協議」によって分けられます。これは、相続人全員の話し合いによって、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めるものです。
相続人同士が仲が悪い場合、この遺産分割協議が非常に困難になります。
- 話し合いが進まない・合意できない
感情的な対立があるため、冷静な話し合いができません。相手の意見を聞き入れず、自分の主張ばかりを押し通そうとするため、いつまで経っても合意に至りません。 - 感情的なもつれが法廷闘争に発展
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所での調停や審判に移行することになります。これは、時間も費用も精神的な負担も大きいプロセスです。故人の財産が、争いの道具となってしまう悲しい事態を招きます。 - 手続きが長期化し、財産が凍結される
遺産分割協議がまとまらない間は、原則として遺産は凍結された状態になります。預貯金の引き出しや不動産の売却・名義変更などができず、相続人全員が困る事態に陥ります。 - 故人の意思が無視される可能性
あなたが「こうしてほしい」と生前に伝えていたとしても、遺言書がなければ法的な拘束力はありません。仲の悪い相続人同士が、自分の都合の良いように解釈したり、無視したりする可能性も出てきます。
③不動産の割合が大きい
不動産は、預貯金のように簡単に分割できるものではありません。そのため、遺言書で明確に「誰にどの不動産を相続させるか」を指定しておかなければ、残されたご家族に大きな負担とトラブルの種を残してしまうことになります。
遺産分割協議での話し合いにおいて、相続人それぞれが「あの不動産が欲しい」「この不動産は価値が高いから自分が」といった主張をし、話し合いがまとまらないことが多々あります。 もし話し合いがまとまらないまま放置されると、不動産が相続人全員の共有名義になってしまう可能性があります。共有名義の不動産は、以下のような問題を引き起こします。
- 売却や活用が困難
共有者全員の同意がないと、売却や大規模なリフォームなどができません。一人でも反対すれば、何も進められなくなります。 - 将来の相続でさらに複雑化
共有者の誰かが亡くなると、その人の相続人がさらに共有者となり、権利関係がねじれてしまいます。世代を重ねるごとに、手の付けられない「塩漬け不動産」になってしまうリスクがあります。 - 固定資産税などの負担
共有者全員が納税義務を負いますが、誰がどれだけ負担するかで揉めることもあります。
④子どもがいない夫婦
日本の民法では、相続人の順位が以下のように定められています
| 順位 | 相続人の種類 | 配偶者との関係 |
| 第1順位 | 子ども | 配偶者と子どもが相続人 |
| 第2順位 | 両親 | 配偶者と両親が相続人 |
| 第3順位 | きょうだい | 配偶者ときょうだいが相続人 |
つまり、子どもがいない場合、親やきょうだいが相続人になるため、配偶者が単独で全財産を相続できるとは限りません。
遺言書がなければ、義理の両親もしくは義理のきょうだいと遺産分割協議を行わなくてはなりません。いくら仲がよくても所詮は他人ですので、残された配偶者にとっては気が重いことでしょう。疎遠であればなおさらです。
⑤前妻との間に子どもがいる
民法上、子どもは親の財産に対する第一順位の相続人です。これは、故人が離婚していても、子どもとの親子関係が続いている限り変わりません。つまり、元配偶者との間の子どもも、現在の配偶者との間の子どもも、等しくあなたの法定相続人となります。
遺言書がない場合は、例によって遺産分割協議を行う必要がありますが、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 前妻の子どもとの関係性
普段から交流があればまだしも、疎遠になっている場合、突然の連絡で遺産分割の話をすることになり、感情的な摩擦が生じやすいです。 - 現在の家族との感情的な対立
現在の配偶者やその間の子どもからすると、「なぜ、今まで関わりのなかった元配偶者の子どもに財産を渡さなければならないのか」という不満や抵抗感が生まれる可能性があります。
⑥事実婚のパートナーがいる
遺言書がない場合、あなたの財産は、民法で定められた「法定相続人」にしか引き継がれません。
長年、一緒に生活しているなど事実上の婚姻関係があっても婚姻届を提出していない事実婚のパートナーは法定相続人ではないため、残念ながら、故人の財産を相続することはできません。
つまり、遺言書がなければ、故人の財産は、故人の親族にしか引き継がれず、長年連れ添った事実婚のパートナーには、一円も渡らないことになります。
さらに、自宅があなた名義であれば、その自宅は故人の親族のものとなり、パートナーが住み続けられなくなる可能性も出てきます。
まとめ
長くなってしまうので、今回の記事はここまでとしまして、後日残りのケースについて掲載いたします。
実際に遺言書の作成を検討したいという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの想いを丁寧にヒアリングし、最適な遺言書の作成をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで