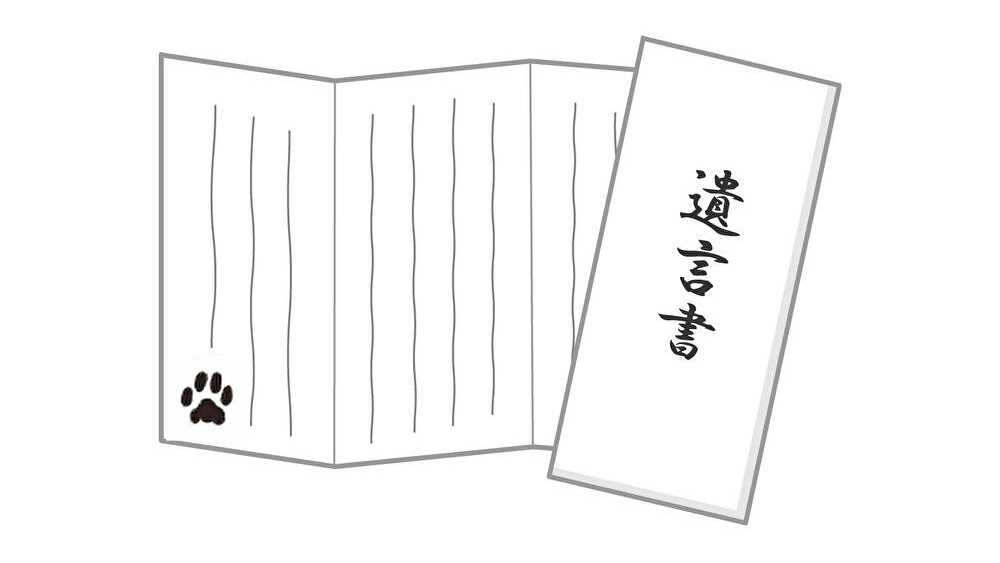こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
「遺言書を作成したいけれど、どこに保管すれば安全だろう?」「もし紛失したり、誰かに改ざんされたらどうしよう…」
このように、自筆で遺言書を作成しようと考えている方にとって、その「保管」は大きな悩みの種でした。しかし、ご安心ください!2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」をご存知でしょうか?
この制度は、法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるというもので、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大きく減らすことができます。今回はこの「自筆証書遺言書保管制度」について、その概要からメリット・デメリット、利用方法、そして注意点を解説していきます。
ご自身の思いを確実に未来へ繋ぐためにも、ぜひ最後までお読みください。
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で作成した自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度です。これにより、自筆証書遺言の課題であった「紛失」「隠匿」「改ざん」のリスクが大幅に軽減され、遺言書の安全性と確実性が高まりました。
自筆証書遺言の課題
制度のメリットを理解するためにも、まずは自筆証書遺言が抱える課題を確認しておきましょう。
- 紛失・隠匿のリスク
自宅で保管する場合、火災や災害などで紛失、遺族によって隠されてしまう、あるいはそもそも遺言書が発見されないリスクがあります。 - 改ざんのリスク
誰かに発見された場合、内容を書き換えられたり、破棄されたりする可能性があります。 - 検認手続きの必要性
自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、基本的に開封することも、内容を確認することもできません。この検認手続きには時間と手間がかかります。 - 形式不備による無効のリスク
法律で定められた厳格な形式に則って作成されていない場合、遺言書自体が無効となってしまうリスクがあります。
これらの課題を解決するために導入されたのが、自筆証書遺言書保管制度なのです。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
この制度を利用することで、自筆証書遺言の課題がどのように解決されるのか、具体的に見ていきましょう。
遺言書の紛失・隠匿・改ざんのリスクがなくなる
法務局という公的な機関が遺言書を厳重に保管してくれるため、紛失や隠匿、改ざんの心配がありません。これにより、ご自身の意思が確実に未来へ伝えられるという大きな安心感が得られます。
相続開始後の「検認手続き」が不要になる
保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所での「検認手続き」が不要になります。これにより、遺族が遺言書の内容を実現するための手間と時間を大幅に短縮できます。これは、遺族にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。
遺言書の形式不備のリスクを軽減できる
遺言書保管官は、遺言書が法律で定められた形式(日付、氏名、押印、全文自書など)に適合しているかを確認してくれます。形式不備によって遺言書が無効になるリスクを未然に防ぐことができるため、安心して遺言書を作成できます。ただし、内容の有効性までは審査されない点には注意が必要です。
遺言者が生存中、いつでも閲覧・撤回・変更が可能
保管された遺言書は、遺言者本人が生存している間であれば、いつでも閲覧したり、撤回したり、変更したりすることができます。生活状況や家族関係の変化に合わせて、柔軟に遺言内容を見直せるため、安心して利用できます。
※閲覧には手数料がかかります。
※変更は氏名や住所等の変更が可能で、遺言書の内容を変えたい場合は、あらめて保管申請する必要があります。
遺言者が亡くなった際、遺族に通知される仕組みがある
遺言書の保管申請をする際に通知を希望すると、遺言書が保管されている旨を法務局から指定した方へ通知されます。これにより、遺言の存在を知らなかったために遺言が実行されないという事態を防ぐことができます。
費用が比較的安価
公正証書遺言と比較して、法務局での保管費用は1件あたり3,900円と、非常に安価です。手軽に利用できる点も大きな魅力です。
自筆証書遺言書保管制度のデメリット・注意点
多くのメリットがある一方で、いくつかデメリットや注意点も存在します。
内容の有効性までは審査されない
法務局は、遺言書の「形式」については確認しますが、記載された内容が法律的に有効であるか(例えば、遺留分を侵害していないか、特定の財産を特定できていないかなど)については審査しません。
制度利用には本人の出頭が必須
遺言書を法務局に預ける際には、遺言者本人が法務局へ出向いて申請する必要があります。代理人による申請はできません。
自筆証書遺言書保管制度の利用方法
それでは、実際に制度を利用する際の手順を見ていきましょう。
- 遺言書の作成
法律で定められた形式(全文自書、日付、氏名、押印)に則って遺言書を作成します。 - 必要書類の準備
- 遺言書本体
- 住民票の写し
- 本籍地の記載がある住民票の写し(本籍地が法務局管轄外の場合)
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 手数料3,900円
- 法務局への予約
遺言書を保管する法務局(ご自身の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する法務局の遺言書保管所)へ事前に電話で予約を入れます。なお、法務局は松戸市内にもあります。 - 法務局での申請
予約した日時に必要書類と遺言書を持参し、本人確認を受け、遺言書を提出します。形式に不備がないか確認を受け、問題なければ保管されます。 - 保管証の受け取り
遺言書が保管されると、「保管証」が交付されます。この保管証は大切に保管しましょう。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の弱点を補い、その有効性と安全性を飛躍的に高める画期的な制度です。費用も安価で手軽に利用できるため、「遺言書を書きたいけれど、公正証書遺言は費用が高い…」と感じていた方にとっては、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
ご自身の思いを未来へ確実に繋ぎ、大切なご家族が争うことなくスムーズに相続手続きを進められるよう、この制度を賢く活用することをお勧めします。
自筆証書遺言書保管制度は非常に便利な制度ですが、遺言書の内容の有効性や、ご自身の思いが確実に伝わる遺言になっているかについては、法務局では審査されません。
当事務所では、書いてはみたが内容に不安を感じる方には添削サービスを、お任せいただければご希望に応じて遺言書の草案を作成いたします。また、自筆証書遺言書保管のサポートも行っております。
遺言書の作成に関するご相談を随時受け付けております。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な遺言書作成をサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です!お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで