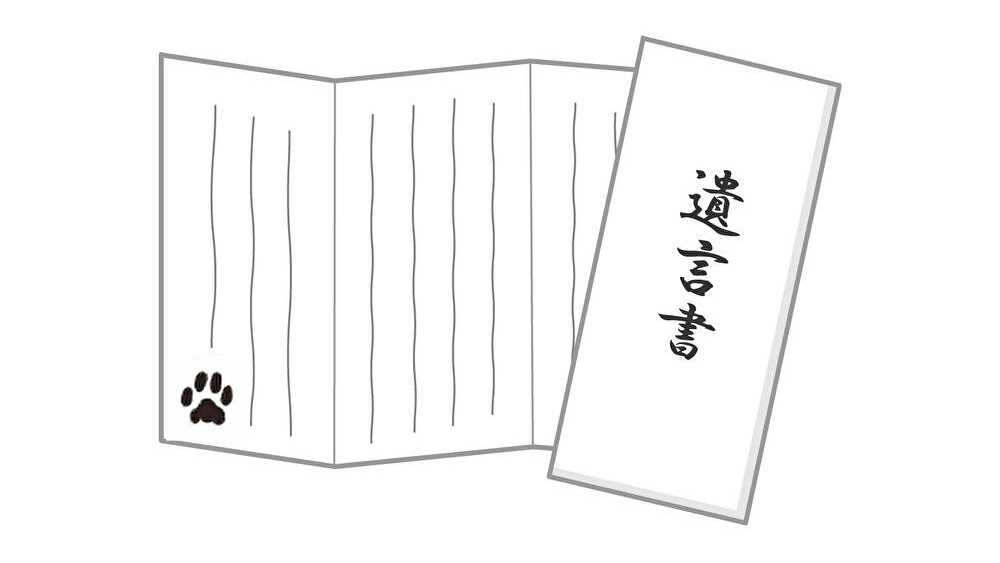こんにちは、行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
今回は「手軽に書ける」というイメージがある自筆証書遺言についてご紹介します。費用もかからず、誰にも内容を知られずに作成できますが、その手軽さの裏に、法的な有効性や保管方法など、せっかく書いたのに無効になってしまうリスクもあります。
メリット・デメリットや注意すべき点をしっかりと理解し、ご自身の状況に合った遺言書の形式を選ぶための参考にしてください。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者本人がその全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで成立する遺言書です(民法968条)。証人の立ち会いも不要で、特別な様式も定められていないため、紙とペン、印鑑があればすぐに作成できるのが最大の特長です。
自筆証書遺言のメリット
手軽に作成できる
これが自筆証書遺言の最大のメリットと言えるでしょう。公証役場への予約や証人の手配なども不要で、思い立った時にすぐに作成できます。
内容を誰にも知られずに作成できる
遺言書の作成から保管まで、基本的に遺言者一人で行うことができます。遺言の内容を家族や第三者に知られることなく、秘密裏に作成したい場合に適しています。
何度でも書き直しができる
遺言の内容は、遺言者の意思が変わるたびに何度でも書き直すことができます。以前の遺言書を破棄したり、新しい日付で作成し直したりすることで、常に最新の意思を反映させることが可能です。
費用がかからない(ほぼ)
公証役場の手数料や証人への謝礼などが一切不要なため、費用を抑えたい方にとっては大きなメリットとなります。
自筆証書遺言のデメリット・注意点
手軽さが魅力の自筆証書遺言ですが、その反面、デメリットや注意点も存在します。これらを十分に理解しておかないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。
法的な要件を満たさないと無効になる可能性が高い
民法には、自筆証書遺言の形式に関する厳格な要件が定められています。
- 全文自筆
遺言書の本文は、遺言者本人が手書きする必要があり、代筆は認められていません。ワープロやパソコンで作成したものは無効です。 - 日付の自筆
作成した年月日を正確に自筆で記載する必要があります。「令和六年五月吉日」のような曖昧な記載は無効とされる可能性があります。 - 氏名の自筆
遺言者本人の氏名を自筆で記載する必要があります。 - 押印
遺言者本人の印鑑(実印である必要はありません)を押す必要があります。
これらの要件が一つでも欠けていると、遺言書全体が無効になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
偽造・変造・紛失のリスクがある
自宅などで保管されると、第三者による偽造や変造のリスク、遺言者自身による紛失のリスクがあります。また、遺言者の死後、相続人が遺言書の存在を知らずに、遺産分割協議を行ってしまうこともあります。
検認の手続きが必要
相続開始後、自筆証書遺言に基づいて遺産分割の手続きを進めるためには、必ず家庭裁判所での検認(遺言書の内容を相続人に確認する手続き)を経る必要があります。この検認の手続きには、相続人の調査、申立書の作成、家庭裁判所への出頭など、時間と手間がかかります。また、検認が終わるまで遺言の内容を実行することができません。
遺言者の意思能力が争われる可能性がある
自筆証書遺言の作成時に、遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があったかどうかについて、相続人間で争いが生じる可能性があります。特に、遺言者が高齢であったり、病気を患っていたりする場合、他の相続人から「遺言作成当時は認知症が進んでおり、遺言能力がなかったのではないか」といった主張がなされることがあります。公正証書遺言のように、公証人が遺言者の意思能力を確認するプロセスがないため、後々紛争の火種となる可能性があります。
書き間違え時の修正
修正する際は、遺言者がその場所を指示し、これを付記して署名することが義務付けられています(民法968条3項)。
- 修正箇所の指示
修正したい文字の近くに、どこをどのように修正したかを明確に示します。例えば、「第1項中『〇〇』を『△△』に訂正」のように記述します。 - 付記
指示した内容を、遺言書の末尾または修正箇所の近くに追記します。 - 署名
付記した部分に、遺言者が自筆で署名します。この署名は、本文の署名と同じものである必要があります。
上記を守らないと無効になってしまいますが、これらの通りに修正するのは面倒で、間違いも起こりやすいので、遺言書全体を書き直すことをお勧めします。
このような手間をかけなくてもよいように、下書きをしたうえで遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書文例
基本的な遺産分割のケースでの遺言書例です。
遺言書
遺言者 遺言太郎 は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、下記の不動産を長男 遺言一郎に相続させる。
所在:〇〇県〇〇市〇〇町
地番:〇〇番
種類:宅地
地積:〇〇㎡
2. 遺言者は、下記の預貯金を長女 遺言花子に相続させる。
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号:△△△△△△
2025年1月1日
遺言者 遺言太郎㊞上記のように相続財産を本文に書かずに、別紙にまとめること(財産目録といいます)もできます。財産目録はパソコンでの作成、登記事項証明書や預金通帳のコピー添付が認められていますので、手書きを減らすこともできます。
自筆証書遺言作成の際の注意点
- 財産の特定
不動産であれば登記簿謄本の記載通りに、預貯金であれば金融機関名、支店名、口座番号を正確に記載します。 - 相続人の正確な記載
相続人の氏名を戸籍謄本通りに記載します。 - 保管場所
作成した遺言書は、紛失や改ざんのリスクがない安全な場所に保管します。法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用することも有効な手段です。 - 定期的な見直し
遺言者の財産状況や家族構成が変わった場合は、遺言書の内容を見直す必要があります。
まとめ
自筆証書遺言は、ご自身の想いを手軽に形にできる有効な手段です。しかし、法的な要件をしっかりと理解し、不備のないように作成する必要があります。
当事務所では、自筆証書遺言の添削サービスやご希望をふまえ、形式・内容ともに法的に有効な遺言書の草案を作成いたします。遺言書の作成に不安がある場合や不明点があればご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで