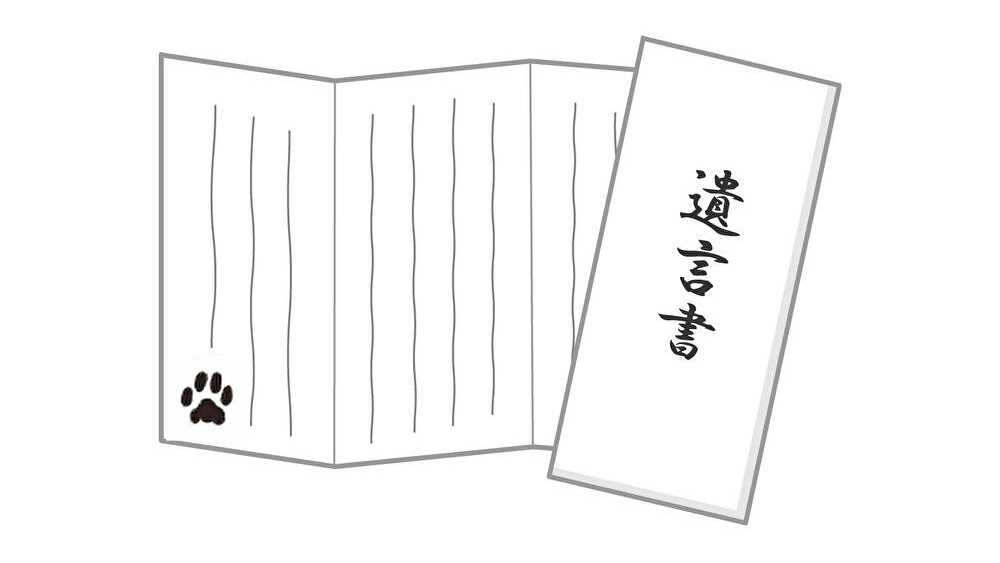こんにちは、行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
今回は遺言書についてです。
「遺言書」と聞くと、多くの方が財産の分け方を指定するもの、つまり「相続」の手続きを思い浮かべるかもしれません。もちろん、遺産分割は遺言書の最も重要な役割の一つですが、実は遺言書はもっとできることがあるのです。それらをご案内していきます。
相続に関すること
遺産の分割方法の指定
最も一般的な遺言の目的は、亡くなった後の遺産を誰にどのように相続させるかを決めることです。遺言の内容は法定相続分や遺産分割協議書よりも優先されます。遺言があれば、特定の財産を特定の相続人に相続させたり、法定相続分とは異なる割合で分割することができます。
- 遺産分割の指定
「自宅の土地・建物は長男に、預貯金は長女に相続させる」といった具体的な指定が可能です。不動産を売却してその代金を長男と長女で分割することや遺産に不動産しかない場合に、不動産は長男に相続させるが、長男が長女に代償金を支払うという指定も可能です。長男と長女で土地を共有するという指定も可能ですが、後々のトラブルに発展する可能性がありますので、共有はおススメしません。 - 相続分の指定
法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することができます。「妻に遺産の3分の2、長男に3分の1を相続させる」といった指定が可能です。
なお、両者ともに分割内容を第三者へ委託することもできます。
相続人の廃除・廃除の取消し
故人に対して虐待や重大な侮辱を加えたなどの非行があった相続人については、家庭裁判所の審判によって相続権を失わせる「相続人の廃除」という制度が民法で定められています。遺言によって、この相続人の廃除の意思表示をすることができます。また、生前に廃除した相続人について、遺言でその廃除を取り消すことも可能です。
配偶者居住権の設定
配偶者居住権とは、故人がその所有する建物に住んでいた配偶者が、一定期間または終身にわたり、その建物に無償で住み続けることができる権利です。2020年4月1日に施行された改正民法によって新設された制度で、高齢化が進む現代において、残された配偶者の生活の安定を図ることを目的としていて、遺言で設定することができます。
遺産分割の禁止
遺言で5年間の遺産分割を禁止することができます。未成年者は遺産分割協議に参加できず特別代理人を選任しなければならないため、成人になるまで協議を保留したいという場合に、使われることがあります。
禁止期間は相続財産が共有状態になることと、相続税の特例を受けるためには「申告期限後3年以内の分割見込書」や「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を申請しなければならず、注意が必要です。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するために、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺産の管理、名義変更手続き、遺産の分配など、遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利と義務を負います。特に、相続人が複数いる場合や、遺産の内容が複雑な場合には、遺言執行者を指定しておくことで、スムーズな遺産承継が期待できます。
相続以外による遺産の処分に関すること
法定相続人に財産を渡すことを「相続」といいますが、法定相続人以外(孫、お世話になった友人、入居していた介護施設やNPO団体など)に財産を渡すことを「遺贈」といいます。遺贈先とその内容を遺言で指定することができます。
身分関係に関する事項
認知
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、父親からの認知を受けることで法律上の親子関係が生じ、相続権を得ます。父親は、遺言によってこの認知を行うことができます。
未成年の後見人の指定
未成年者に親権者がいない場合や、親権者がいても管理権がない場合に、未成年者の財産管理や身上監護を行う後見人を選任する必要があります。遺言によって、未成年者の後見人や後見監督人を指定することができます。
その他のこと
祭祀承継者の指定
祖先を祀るための位牌、仏壇、墓地などは、法律上の相続財産とは異なり、「祭祀財産」と呼ばれます。誰がこの祭祀財産を受け継ぐかは、慣習に従うことが多いですが、遺言によって祭祀承継者を指定することもできます。
付言事項
遺言書の本文とは別に、「付言事項」として、相続人へのメッセージや、財産に対する思い入れ、葬儀や納骨に関する希望などを記載することができます。介護に従事してくれた長男に他のきょうだいよりも多めの遺産を渡したいなど、取り分が少ない相続人には不満が生じやすくなります。しかし、そのような内容の遺言を作成した理由を付言事項に書くことで、相続人の不満が解消されることも少なくありません。付言事項には法的拘束力はありませんが、残された家族への心のこもったメッセージとして、紛争の予防や円満な解決に繋がることもあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
このように、遺言書は単に財産を分けるための書類ではなく、あなたの様々な想いを残された家族へ伝える大切な手段となるのです。
遺言書についてもっと詳しく知りたい、あるいは実際に遺言書の作成を検討したいという方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。あなたの想いを丁寧にヒアリングし、最適な遺言書の作成をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで