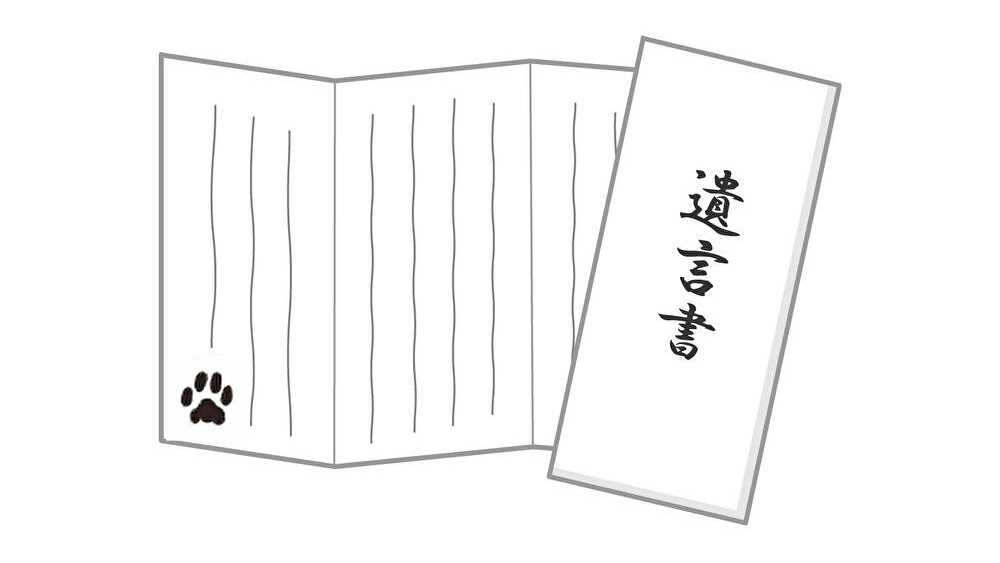こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
以前、下記にてドラマで突っ込みを入れたくなるようなシーンがあることを触れました。
今回は、もう一つの「遺言書を勝手に開けちゃダメ」についてです。
あるお金持ちが亡くなり、葬儀が終わった後に家族が一堂に会し、静まり返る中、弁護士がおもむろに「故人から遺言書を預かっており、本日はそれをみなさまにお知らせするためにお集まりいただきました。」と切り出します。家族がかたずをのんで見守る中、遺言書の入った封筒を開封し、読み上げます・・・
昔の2時間ドラマなどでよくあったシーンですが、この弁護士の行為は法律違反の可能性があります。
遺言書は故人の最後の意思表示であり、その取り扱いには細心の注意が必要です。特に、遺言書を「勝手に開ける」行為は、法的な問題を引き起こす可能性があるため、絶対に避けるべきです。今回は、遺言書の正しい取り扱いと、勝手に開けてしまうことのリスクについて解説します。
遺言書の種類と正しい保管方法
遺言書には一般的に使われる以下の2つの種類があります。
自筆証書遺言
文字通り、遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。
- メリット
費用がかからず、手軽に作成できます。 - デメリット
要式を満たしていないと無効になったり、紛失・隠匿・改ざんのリスクがあったりします。
【保管方法】 以前は自宅などで保管されることが多く、これが「勝手に開けられる」原因となることがありました。しかし、2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で安全に保管してもらうことができます。この制度を利用すると、遺言書が偽造・変造される心配がなく、相続発生時にも相続人への通知が行われるため、遺言書の存在が埋もれることもありません。
公正証書遺言
公証役場で、公証人が遺言者の意思に基づいて作成する遺言書です。
- メリット
法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配がありません。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。 - デメリット
作成に費用がかかり、証人2人が必要です。
【保管方法】 原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されますが、これらは単なる写しであり、開封することに問題はありません。
なぜ遺言書を「勝手に開けてはいけない」のか?
自筆証書遺言で封印されているものについては、相続人が勝手に開封してはいけません。これには明確な法的根拠と理由があります。
法的な義務違反(民法第1004条)
民法第1004条には、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち会いがなければ、開封することができない。」と明記されています。
つまり、自筆証書遺言で封がされている遺言書は、家庭裁判所の「検認」という手続きを経ずに開封してはならない、という法律上の義務があるのです。
過料(罰金)の可能性
上記の義務に違反して、勝手に遺言書を開封した場合、民法第1005条により5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。これは刑事罰ではありませんが、法律違反として行政処分を受けることになります。
遺言書の無効化のリスク
勝手に開封したからといって、遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありません。しかし、開封時に不必要な書き込みをしてしまったり、意図せず破損させてしまったり、あるいは内容を改ざんしたと疑われるような事態が生じたりする可能性があります。
万が一、遺言書の内容に疑義が生じ、裁判などで争いになった場合、「勝手に開封した」という事実が不利に働く可能性もゼロではありません。遺言書は故人の最後の意思を示す重要な書類であり、その有効性が争われることは、相続人全員にとって大きな負担となります。
相続人間の不信感とトラブルの発生
遺言書を勝手に開封することは、他の相続人に対して「何かを隠しているのではないか」「自分に有利になるように改ざんしたのではないか」といった不信感を与えかねません。これにより、円満な相続が困難になり、感情的な対立や、場合によっては遺産分割協議が泥沼化する原因となります。相続はただでさえデリケートな問題であり、こうした不必要な火種は避けるべきです。
遺言書を隠匿・改ざんする意図がなくても疑われる
たとえ善意で、あるいは単なる好奇心で開封してしまったとしても、他の相続人からは「故人の意思を歪めようとしたのではないか」と疑われる可能性があります。一度疑念が生じると、その後の話し合いは非常に難しくなります。
自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書の場合
前述の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に預けられた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要となります。これは、法務局が遺言書の形式的な不備を確認し、安全に保管してくれるため、偽造や変造の恐れがないためです。
相続発生後、法務局に遺言書が保管されていることが判明した場合、相続人や受遺者は法務局で「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。この証明書は遺言書の内容を法的に証明するものであり、検認を経た遺言書と同等の効力を持つとされています。
この制度を利用していれば、相続人が遺言書を探し回る必要もなく、また勝手に開封してしまうリスクもありません。遺言書の作成を考えている方は、この制度の利用を強くお勧めします。
もし遺言書を見つけたらどうすべきか?
自宅などで遺言書を発見した場合、たとえ封がされていなくても、安易に開封せずに以下の手順を踏むようにしましょう。
- 落ち着いて、遺言書が封筒に入っているか確認する。
もし封がされていれば、絶対に開封しないでください。 - すぐに他の相続人全員に連絡し、遺言書を発見した旨を伝える。
情報を共有することで、後々のトラブルを防ぎます。 - 家庭裁判所に「遺言書の検認」を申し立てる。
遺言書が封をされていなくても、自筆証書遺言は原則として検認が必要です。 - 家庭裁判所の指定する検認期日に、遺言書を持参する。
相続人全員が立ち会うことが原則です。
公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されているため、これらの手続きは不要です。相続人または受遺者は、公証役場に問い合わせて遺言書の有無を確認し、写しの交付を受けることになります。
まとめ
遺言書は、亡くなった方が残した最後のメッセージであり、その意思を尊重することが最も大切です。しかし、感情的になったり、知識が不足していたりすると、誤った行動に出てしまうことがあります。
「勝手に開けてはいけない」ことは、単なるルールではなく、故人の意思を尊重し、相続人間の公平性を保ち、無用なトラブルを避けるための重要な警告です。
冒頭のドラマのシーンに戻りますと、おそらく故人の自筆証書遺言を弁護士に託しているが、検認手続きはまだしていないと思われますので、検認前の開封という弁護士の行為は法律に違反するものです。
だからといって、ケチをつけるつもりは全くありません。検認の手続きのくだりをドラマに入れても時間の無駄でしょうから、「勝手に開けてはいけない」ということを知ってもらえたらと思います。
遺言書の発見から相続手続きまで、不安な点があれば、ご相談ください。適切な手続きと相続人間の円満な解決をサポートいたします。故人の思いが正しく実現されるよう、冷静かつ慎重な対応を心がけましょう。
初回の相談は無料です!お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで