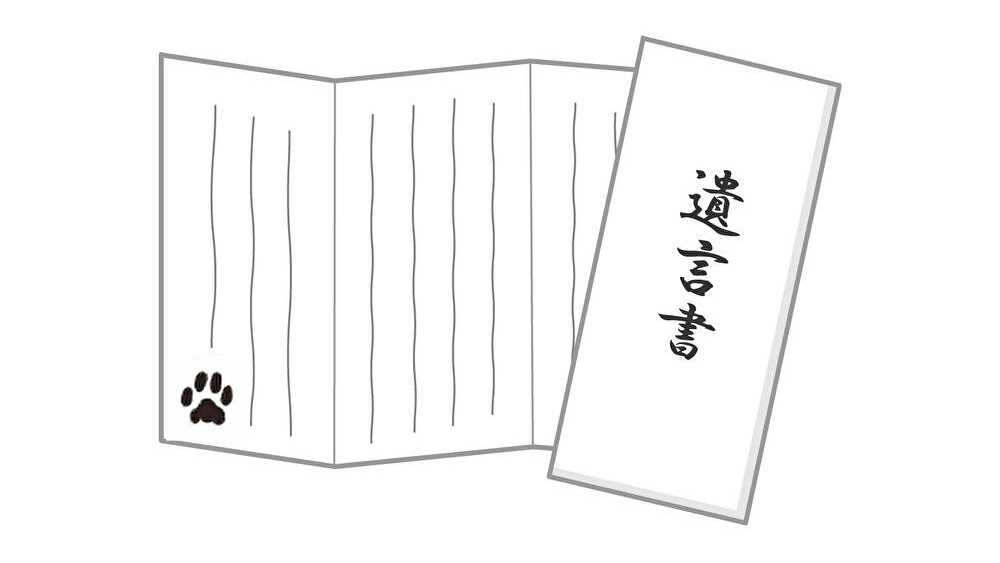こんにちは 行政書士わたなべ事務所の渡辺晋太郎です。
あるお金持ちが亡くなり、葬儀が終わった後に家族が一堂に会し、静まり返る中、弁護士が故人から預かっていた遺言書を開封し、読み上げます。遺言書には「愛人に全部財産を譲る!」と書かれていて、財産を巡る争いが勃発する。。。
ひと昔前の2時間ドラマなどでよくあったシーンですが、「本当にあなたは弁護士ですか?」と突っ込みを入れたくなるところが2か所あります。
今回はそのうちの一つ「遺留分(いりゅうぶん)」についてです。
「愛人に全財産を譲る!」など遺言書にはご自身の最終的な意思を自由に記すことができます。しかし、その「自由」には一定の制限があることをご存じでしょうか?
それが、相続人に保障された最低限の取り分である「遺留分」です。この遺留分を無視して遺言を作成してしまうと、故人の想いが実現しないだけでなく、残された家族の間で深刻な争いに発展するリスクがあります。
遺言作成時に「遺留分」をなぜ考慮すべきなのか、その仕組みと、遺留分を侵害してしまった場合の対処法、そしてトラブルを避けるための対策について、詳しく解説いたします。あなたの想いを確実に未来へ届けるために、ぜひ最後までお読みください。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、法律によって保障された最低限の遺産取得分のことです。たとえ遺言書で「全財産を第三者に与える」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、その権利を主張することができます。
これは、被相続人の財産形成に貢献した家族の生活保障や、相続人の期待権を保護するための制度です。
遺留分を持つ人(遺留分権利者)
遺留分を持つことができるのは、以下の法定相続人です。
- 配偶者
- 子(直系卑属)
被相続人の子、子が既に亡くなっている場合は孫、ひ孫(代襲相続人) - 直系尊属
被相続人の親、親が既に亡くなっている場合は祖父母(ただし、子がいる場合は直系尊属には遺留分はありません)
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続人の組み合わせによって異なります。
| 相続人のパターン | 遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 配偶者と子ども | 配偶者:1/4 子ども:1/4 |
| 配偶者と父母 | 配偶者:1/3 父母:1/6 |
| 配偶者ときょうだい | 配偶者:1/2 きょうだい:なし |
| 子どものみ | 1/2 |
| 父母のみ | 1/3 |
| きょうだいのみ | なし |
相続人が複数いる場合は、それぞれの人数で按分します。例えば、夫が亡くなり、妻と子が2人いる場合、遺留分は妻が財産の1/4、子がそれぞれ財産の1/8(子全体の1/4を2人で分けるため)となります。
冒頭のドラマの話に戻りますと、弁護士であれば相続人に対して、「遺言書はこうなっていますが、あなた方にも取り分はありますよ」くらいのことを言えないといけないですのですが、そんなことをするとドラマとして成立しないので、スルーされているのでしょうね。
ですので、ケチをつけるつもりは全くありません。もし自分が同じような状況に置かれたとしても「配偶者、子には最低限の取り分がある」ことを知ってもらえたらと思います。
なぜ遺言作成時に遺留分を無視してはいけないのか?
遺留分を考慮せずに遺言を作成すると、以下のような問題が生じる可能性があります。
相続人間の紛争リスクが高まる
遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者はその不足分を請求することができます。これが「遺留分侵害額請求」です。
- 遺留分侵害額請求は金銭債務に変わる
遺留分侵害額請求は、原則として金銭で支払います。財産を多く受け取った相続人や受遺者は、他の相続人から金銭の支払いを求められることになります。 - 感情的な対立
金銭の請求は、しばしば相続人間の感情的な対立を深め、親族関係を破綻させる原因となります。せっかく遺言で争いを避けようとしても、かえってトラブルを招いてしまう可能性があります。
故人の意思が完全に実現できない可能性がある
遺言書で特定の財産を特定の人物に与えようとしても、遺留分侵害額請求によって金銭での支払いが必要となれば、その財産を売却して資金を捻出したり、別の財産を取り崩したりする必要が出てくるかもしれません。結果として、故人が意図した通りの財産承継が実現できない可能性が出てきます。
手続きの長期化と負担増
遺留分侵害額請求が発生した場合、当事者間の話し合いで解決できないと、最終的には調停や訴訟に発展する可能性があります。これにより、相続手続きが長期化し、精神的・経済的な負担が増大することになります。
遺留分を侵害してしまったら?
もし、あなたが作成した遺言書が原因で、あるいはあなたが相続人として遺留分を侵害されたと感じた場合、どのように対処すればよいでしょうか。
遺留分侵害額請求の行使
遺留分権利者は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に、遺留分を侵害した相手方に対して遺留分侵害額請求を行います。これは、内容証明郵便などで意思表示をするのが一般的です。
話し合い
まずは、当事者間で話し合いを行い、金銭での支払い方法や金額について合意を目指します。互いの主張を理解し、円満な解決を図ることが最も望ましいです。
家庭裁判所での調停・審判
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停委員を介して話し合いを進め、合意を目指します。それでも解決しない場合は、訴訟(審判)へと移行することになります。
遺留分によるトラブルを避けるための対策
遺言作成時に遺留分を考慮し、将来のトラブルを未然に防ぐための対策を講じることが重要です。
遺留分を侵害しない内容にする
最も基本的な対策は、遺言書の内容が遺留分を侵害しないように作成することです。遺産全体の評価額を把握し、各相続人の遺留分額を計算した上で、財産の配分を決めましょう。
付言で想いを伝える
もし、特定の相続人への配分を少なくせざるを得ない場合や、特定の財産を特定の人物に遺したい強い理由がある場合は、遺言書の「付言(ふげん)」を活用しましょう。
付言とは、遺言書の本文の後に書かれることが一般的ですが、「なぜこのような遺言にしたのか」に対する故人の真意や感謝の気持ちを記すことを指します。
付言には法的な効力はありませんが、残された家族が遺言者の真意を理解し、納得しやすくなります。これにより、遺留分侵害額請求を抑止したり、請求されても話し合いで円満解決しやすくなったりする効果が期待できます。
まとめ
遺言書は、ご自身の最終的な意思を実現し、残された家族の負担を減らすための重要なツールです。しかし、その作成にあたっては、「遺留分」という法的な制限を理解しておくことが不可欠です。
遺留分を無視した遺言は、かえって家族間の争いを招き、故人の想いが実現できない事態に繋がりかねません。
当事務所では、書いてはみたが内容に不安を感じる方には添削サービスを、お任せいただければご希望に応じて遺言書の草案(もちろん遺留分を侵害しません!)を作成いたします。
遺言書の作成に関するご相談を随時受け付けております。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な遺言書作成をサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です!お気軽にご連絡ください。
詳しくは行政書士わたなべ事務所まで